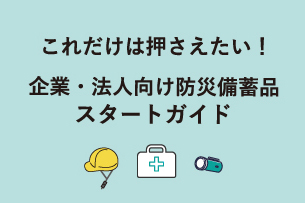企業の防災用品備蓄は努力義務!社内に備えたい非常食や防災グッズを紹介
企業の防災用品備蓄は努力義務!社内に備えたい非常食や防災グッズを紹介

企業には、所在地の自治体によって防災用品を備蓄する努力義務が定められています。火災や地震、台風など、思わぬ天災で社内での避難生活が必要になる可能性があるため、防災用品を備蓄しておき、いざという時のために従業員の安全を確保できる体制を整えることが重要です。 備蓄が必要な防災用品は、一般的に1人あたり3日〜1週間分程度と言われています。今回は、企業に求められる防災用品や最低限必要なものなどについて解説します。
企業が防災備蓄品を準備するのは義務?

企業が防災備蓄品を準備することは、法律上の「義務」ではなく一般的に「努力義務」とされています。しかし、労働契約法第5条や労働安全衛生法第3条に基づく安全配慮義務により、企業は従業員の安全と健康を確保する責任を負っており、災害時の安全確保もこの責務の一環と解釈されます。
地方自治体の条例でも、防災備蓄の準備を事業者の努力義務として位置づける例があり、法的強制力はないものの企業の果たすべき社会的責任として重要だとされています。
企業が防災備蓄品を準備しておく必要性

ここでは、企業が防災備蓄品を準備しておく必要性を解説します。
従業員の安全を確保するため
企業が防災備蓄品を準備しておく最大の理由は、従業員の安全を確保することです。地震や火災、台風などの災害が発生した際、食料品や救急医療用品、毛布、簡易トイレなどの備蓄がなければ、従業員は長時間にわたり安全を確保できず、健康や生命に直接的な危険が及ぶ可能性があります。特に災害発生直後は、交通網の寸断や通信の途絶などにより、外部からの支援がすぐに届かない場合もあります。そのため、社内で一定期間自力による避難生活ができる備蓄を整えておくことが不可欠です。
備蓄があることで、従業員は落ち着いて避難行動ができ、応急処置や連絡手段の確保など緊急対応も行えるようになります。これにより、怪我や混乱のリスクを最小限に抑え、被災時の安全性を高めるとともに、企業としての安全配慮義務を果たすことにもつながります。
救助活動の妨げにならないようにするため
企業が防災備蓄を行うことは、救助活動を円滑に進めるうえでも重要です。災害直後は、救助隊や消防・自治体の人員は人命救助を最優先として多数の被災者対応に追われます。災害時に従業員が命をつなぐ物資を自力で確保できる状態であれば、外部の救助隊や自治体の支援を待つ必要が減り、現場での混乱を軽減できます。
また、備蓄が整っていることで、従業員が自力で避難や初期対応を行えるため、自治体などの支援資源に余裕を生み出し、地域全体の安全確保にも貢献します。さらに、平常時における備蓄品の管理や運用を通じて従業員の防災意識が向上することも災害時の適切な行動につながり、救助活動や避難誘導をスムーズに行える体制づくりに寄与します。
事業を短期間で復旧させるため
防災備蓄は、企業の事業継続計画(BCP)の一環としても極めて重要です。事業継続計画とは、災害発生時に企業の重要業務を維持・復旧させるための具体的な行動計画を指します。災害発生後、従業員が安全を確保できる環境と物資が整っていれば、事業活動の再開が迅速に行えます。たとえば、食料品や水、簡易トイレ、毛布、非常用照明などの備蓄は、従業員が安心して職場に留まり、業務復旧に集中できる基盤となります。これにより、操業停止による損失や納期遅延などの経済的影響を軽減できるほか、取引先や顧客への影響も抑えられます。
また、備蓄の整備は従業員の安心感や士気を高め、災害後の職場秩序の維持にもつながります。結果として、企業は社会的責任を果たしながら、迅速かつ計画的に事業を復旧させることが可能となります。
企業の防災用品チェックリスト

企業の防災用品は、災害備蓄品の代表例とされる食料品や、防護・救護品・生活用品などに分かれます。備蓄漏れがないよう十分に準備しましょう。
ここでは、項目ごとに整備しておきたい防災用品のチェックリストをご紹介します。
食料品・非常食
一般的に、1人あたりに必要な食料品の備蓄は3日~1週間分とされています。
これは、災害が起こってから3日間は人命救助が最優先とされるため、水や食料など物資の配布は望めない可能性が高いこと、また1週間程度はライフラインの復旧やスーパーマーケットなどにおける通常の物流が再開せず、物資の調達が難しい場合があることなどが理由です。
備蓄する食料品の例としては、下記のようなものが挙げられます。
■必需品
・水:1人あたり1日3リットル×3日分=9リットル
■主食
・パックご飯(アルファ化米)、カップ麺、乾パン、クラッカーなど:1人あたり3食×3日分=9食
・レトルト食品(カレーなど)、缶詰(肉や魚を中心としたもの):1人あたり3食×3日分=9食
備蓄する食料の量は、企業の立地状況に合わせて増減することも必要です。
特に山間部など市街地から離れた場所は、ライフラインの復旧に時間がかかると考えられるため多めに備蓄しておくと安心です。
防災グッズ・防護・救助品・生活用品
防護・救助品・生活用品としては、下記のようなものを用意するのが一般的です。
・防災用ヘルメット:1人あたり1個
・毛布:1人あたり1枚
・トイレットペーパー:1人あたり3ロール
このほか、簡易トイレ、懐中電灯、ラジオ、非常用電源やスマートフォン用バッテリー、救急用品などを従業員数に応じて適切に備えておきましょう。
救助品としては、ジャッキやバールが含まれるセットを用意しておけば、被災した建物からの救助も行えるようになります。
これらの防災用品を常に用意しておけば、万が一の際でも会社内に留まって安全を確保することができます。
防災用品の社内周知
防災用品を備蓄していることは、社内に積極的に周知しましょう。
災害発生時、防災担当者が必ずしもオフィス内にいるとは限らず、防災用品が用意されていても、従業員に周知されていなければ使うことができません。備蓄している物資の内容や、具体的な保管場所などを従業員一人ひとりが理解しておくことが求められます。
防災備蓄品の詳細なリストは以下のコラムにも掲載しています。
防災備蓄品の準備以外に企業が行うべき防災管理
ここでは、企業が行うべき防災管理をご紹介します。
事業継続計画(BCP)の作成
企業は、防災備蓄品を準備するだけでなく、事業継続計画の作成が不可欠です。たとえば、事業における優先順位を明確化し、代替オフィスや通信手段の確保、必要な資材や人員の手配ルートを事前に定めておくことが求められます。事業継続計画を作成することで、災害発生直後の混乱を最小限に抑え、従業員が取るべき行動が明確になります。
また、BCPは一度策定すれば終わりではありません。社会情勢や事業内容の変化、新たなリスクの出現などに応じて、定期的に見直し、改善を加えることが必要です。これにより、実効性の高い計画として機能し、企業の持続可能性と信頼性を高めることにつながります。
事業継続計画については以下のコラムにも掲載しています。
防災訓練の実施
防災訓練は、従業員が災害時に冷静で的確な行動を取るために欠かせない取り組みです。災害の発生は予測できないため、事前に避難経路や非常口を確認しておくことで、緊急時に従業員が慌てず行動できるようにしておく必要があります。具体的には、避難誘導のシミュレーション、消火器やAEDの使用訓練、負傷者を想定した応急処置の練習などが挙げられます。
こうした訓練を定期的に繰り返すことで、従業員一人ひとりの防災意識を高めるだけでなく、組織全体での連携や役割分担も明確になります。さらに、実際の訓練を通じて事業継続計画や防災マニュアルの不備を発見でき、改善へとつなげることもできます。
オフィスの災害対策の強化
オフィスにおける災害対策は、従業員の安全を守り、被害を最小限に抑えるための重要な取り組みです。たとえば、地震時に転倒や落下の危険がある家具やオフィス機器をしっかり固定し、通路や非常口を常に確保しておくことは最低限必要です。
また、サーバーや通信設備、電源装置など重要インフラの耐震化・冗長化を進めることで、災害後も業務継続の可能性が高まります。火災に備えて火災報知器やスプリンクラー、消火器を適切に配置し、定期的に点検することも欠かせません。さらに、窓ガラスへの飛散防止フィルムの貼付や非常用照明の設置など、従業員が安心して避難できる環境づくりも重要です。
こうした取り組みは従業員の安全性を高めるだけでなく、事業再開までの時間を短縮する効果もあり、企業にとって経済的な損失を抑えることにもつながります。
ハザードマップの確認
企業は、自社が立地する地域にどのような災害リスクがあるのかを把握しておく必要があります。その際に活用できるのが、自治体が公開しているハザードマップです。洪水、津波、土砂災害、地震による揺れの大きさや液状化の可能性などを事前に確認することで、オフィスや従業員にどのような被害が及ぶかを予測できます。これに基づき、避難経路や避難先の選定、オフィス家具や機器配置の見直しを行ったり、必要に応じて備蓄品の種類や数量を調整したりすることが可能です。
さらに、従業員に対してハザードマップを活用した教育を実施することで、自宅からの通勤経路や家族の避難方法についても意識を高められます。災害時の混乱を最小限に抑えるためには、地図を確認するだけではなく、ハザードマップにおける最新情報を定期的に確認し、社内で共有しておくことが重要です。
緊急時の連絡手段の確保
災害発生時の大きな課題のひとつが「情報伝達の途絶」です。従業員や取引先、関係機関と迅速に連絡を取り合う体制を確立しておくことは、企業の防災管理において欠かせません。電話回線やインターネットは災害時に混雑や断絶が発生しやすいため、メールや社内チャットツール、安否確認システムなど複数の手段を用意し、非常時にどれを優先するかを明確化しておく必要があります。
さらに、衛星電話やトランシーバーなど代替通信手段を導入することも有効です。また、緊急時に誰が情報を集約し、どのように伝達するかといった連絡フローを事前に定めておくことで、混乱を避けることができます。
これにより、従業員の安否確認や指示伝達をスムーズに行い、企業として迅速な対応が可能となります。
まとめ

企業の防災用品の備蓄はあくまでも「努力義務」ではありますが、社会的責任や従業員の安全確保を考えれば、日頃から必要量を備蓄しておくことが必要不可欠です。万が一の事態にできるだけ落ち着いて対応するためにも、従業員1人につき3日〜1週間分程度の食料と、防護品や生活用品を用意しておきましょう。
株式会社パソナ日本総務部では、企業向けの防災ソリューションとして「防災備蓄品ワンストップサービス」を提供しています。
法人向け防災備蓄品の新規購入や買い替えの手配、備蓄状況の調査、賞味期限・在庫の管理システム提供、期限切れ前の不用備蓄品の引き取り(諸条件あり)までサポートする、防災分野のトータルアウトソーシングサービスです。「防災備蓄品の重要性は認識しているが、具体的に何から始めればよいかわからない」という企業担当者の皆様は、まずはお問い合わせください。