事業継続計画(BCP)とは?基本策定の4ステップと効果的に機能させるポイント
事業継続計画(BCP)とは?基本策定の4ステップと効果的に機能させるポイント

2021年8月の西日本を中心に発生した集中豪雨、2016年4月の最大震度7を観測し九州地方で多くの被害をもたらした「熊本地震」、2024年1月の最大震度7を観測し石川・富山・新潟などに被害が広がった「能登半島地震」など、日本は自然災害が多い国のひとつです。自然災害が発生するたびに多くの企業が被災し、事業継続が困難となったケースは少なくありません。一方で事業継続計画(BCP)を策定していた企業においては、迅速な初動対応により早期復旧を実現しています。今回は、緊急時の事業継続マニュアルとして機能する事業継続計画(BCP)の基礎知識に加え、事業継続計画(BCP)を策定することのメリットや課題、策定手順・ポイント、業界別に見る事業継続計画(BCP)の具体例などをご紹介します。
事業継続計画(BCP)とは
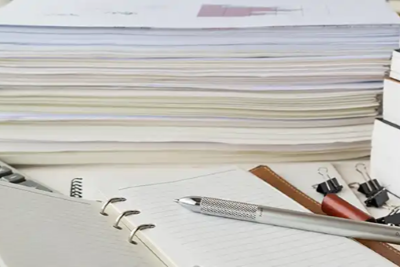
「事業継続計画(BCP)」とは、自然災害などの緊急事態発生時に事業を継続するため、もしくは事業が停止した場合に一刻も早い復旧をするための計画、およびマニュアルそのものを指します。一般に防災対策と混同されてしまいがちですが、これらは別物です。
事業継続計画(BCP)と防災対策とでは、目的や想定する緊急事態の範囲も、取組みにフォーカスする時期も異なります。
事業継続計画(BCP)の目的は、「事業を継続させること」です。
そのため、地震・風水害や感染症の蔓延、テロ攻撃といった一般的に災害として想定される事象のほか、サイバー攻撃や突然の停電、いわゆるバイトテロなどの外的要因・内的要因を問わず、事業を停止させ得るすべての緊急事態が対象となります。
緊急事態が起きた後に、いかに初動対応を迅速におこない事業を継続させるかが問われるため、BCPでフォーカスされるのは「事後対応」です。
対して防災対策の目的は、従業員や顧客の命および施設などの会社財産を守ることです。
従業員たちの安全確保・安否確認に焦点を当てている対策なので、主に自然災害など従業員たちの身の安全が脅かされる緊急事態を対象としています。人や施設などの経営資産が失われないように災害を未然に防ぐこと、被害をなるべく小さくすることを目指して対策をするため、基本的に防災対策は「事前対応」だと言えます。
また事業継続計画(BCP)は事業を継続させるため、自社のあらゆる拠点はもちろん、場合によってはサプライチェーン先や他社と共同で対策を練ることもあります。対して防災対策は、災害などの緊急事態が起き得る拠点ごとの対策を考えることがほとんどです。
事業継続計画(BCP)も防災対策も、どちらも企業防災において重要な要素であり、緊急事態から企業と従業員を守るために必要な取組みです。
関連記事
事業継続計画(BCP)対策が注目された背景

事業継続計画(BCP)の誕生は、1970年代にさかのぼります。「緊急時に事業を継続させるための手法」として、当時アメリカやイギリスで注目されました。それから約30年後の2001年、世界同時多発テロが発生しました。これをきっかけに、全世界の企業が事業継続計画(BCP)の重要性について考えるようになったとされています。
一方、その当時の日本では、事業継続計画(BCP)はほとんど浸透しませんでした。テロ攻撃に対する現実味をあまり感じることができなかったため、事業継続計画(BCP)を重視する国内企業は少なかったようです。本格的にBCPが周知・浸透し始めたのは、2011年3月に発生した東日本大震災以降のこととされています。
「帝国データバンク」が2011年に実施した「 事業継続計画(BCP)についての企業の意識調査」によると、東日本大震災以前に事業継続計画(BCP)を策定した国内企業は、全体の7.8%に留まっていました。一方、2024年に実施した調査では、「策定している」と回答した企業は19.8%となっています。「策定を検討している」まで含めて50.0%と、事業継続計画(BCP)に対する企業意識の高まりが顕著となりました。
近い将来、南海トラフ地震や首都直下型地震など、大規模災害の発生が予測されています。それらへの備えとして、事業継続計画(BCP)の策定を急ぐ国内企業はさらに増加すると考えられます。
事業継続計画(BCP)マニュアルの種類

事業継続計画(BCP)策定時には、その対策方法をマニュアル化することが一般的で、BCPマニュアルにはいくつかの種類があります。 ここでは、「外的要因」「内的要因」「自然災害」に対策する3つのマニュアルについて詳しく解説します。
外的要因のBCP対策マニュアル
「外的要因」とは、サイバー攻撃や通信トラブル、予期しない取引先の倒産、感染症など、自社以外の要因で起こった問題を指しています。特に取引先の倒産は、自社の事業継続を困難にする要因だといえるでしょう。
外的要因のBCP対策マニュアルは、このような外部に起因するトラブルへ対応するために作成します。 例えば、仕入れ先が倒産したときに代替となる企業一覧のリストアップ化や、サイバー攻撃を受けたときのデータ復旧方法などが、外的要因のBCP対策マニュアルに盛り込む事例として挙げられます。
内的要因のBCP対策マニュアル
内的要因とは、ヒューマンエラーや自社設備のトラブル、不祥事をはじめとした社内に起因する問題を指しています。トラブルなどのネガティブな要因だけでなく、システムのバージョンアップなどに伴って、一時的に業務を継続できない状況も内的要因のひとつです。
内的要因のBCP対策マニュアル作成では、取引先や関係先への報告プロセスや謝罪テンプレート作成、プレスリリースなどで情報開示する際の手順整備、取引先や関係先の連絡先一覧と連絡の優先順位決めなどが必要となります。
自然災害のBCP対策マニュアル
自然災害のBCP対策マニュアルは、地震、台風、火災などの災害が起こったときに対処するためのマニュアルです。被災後の被害状況の確認方法や手順、従業員の安否確認方法などをマニュアル化するのが一般的です。 加えて、自然災害によって停止した業務を復旧させるための代替設備は何にするかなどの具体的対応策なども、自然災害のBCP対策マニュアルに含まれます。
関連記事
事業継続計画(BCP)と防災対策・事業継続マネジメント(BCM)の違い
事業継続計画(BCP)と類似するものに、防災対策と事業継続マネジメント(BCM)がありますが、これらは別物です。
防災対策との違い
事業継続計画(BCP)と防災対策の違いは、前述した「BCP対策は事後対応、防災対策は事前対応」に加え、「あらゆるトラブルに対処するためのもの」か「自然災害に対応するためのもの」であるかという点にもあります。
BCP対策は外的要因や内的要因、自然災害といったすべてのトラブルへの対応策を考慮する必要があります。一方、防災対策は基本的に自然災害が起こったときの対応策に限定されます。
またBCP対策は「トラブルが起こったときに、スムーズに事業を復旧させること」を念頭に置きますが、防災対策は人命の確保や資産の保全などが主目的となることも異なる点です。
事業継続マネジメント(BCM)との違い
事業継続計画(BCP)と事業継続マネジメント(BCM)の違いは、「その言葉が表す範囲」にあります。事業継続計画(BCP)は前述のとおり、自然災害などの緊急事態発生時に事業を継続するため、もしくは事業が停止した場合に一刻も早い復旧をするための計画、およびマニュアルそのものを指します。
一方、事業継続マネジメント(BCM)は事業継続計画(BCP)の策定や導入、実際の運用などを含む包括的なマネジメント活動を指します。つまり、事業継続計画(BCP)は「計画」、事業継続マネジメント(BCM)は「マネジメント活動全般」を表すということです。事業継続マネジメント(BCM)の一環として策定されるのが事業継続計画(BCP)と考えるとわかりやすいかもしれません。
関連記事
事業継続計画(BCP)を策定することで得られるメリット
事業継続計画(BCP)を策定した場合、企業は以下のメリットを得られます。
緊急時にも対応可能な経営体制を構築できる
地震をはじめとする自然災害や突発的な事故、テロなどが発生した場合、それらの対応に追われ事業を継続できなくなる可能性があります。被害の大きさによっては損失が膨らみ、最悪の場合は倒産に追い込まれる恐れもあるでしょう。
事業継続計画(BCP)を策定していれば、もし緊急事態が起きても迅速かつ適切に対処することが可能です。事業の維持および早期復旧につながる経営体制を構築できるため、経営へのダメージを最小限に抑えられるでしょう。
従業員が安心・安全に働ける環境を構築できる
緊急事態の影響を受け、事業が縮小または継続不能となった場合、従業員は働く場所と収入源を失ってしまいます。そのため、自らが勤める企業が事業継続計画(BCP)を策定していないとわかれば、従業員が強い不安や不信感を抱く恐れがあるでしょう。
事業継続計画(BCP)を策定していれば、従業員が安心・安全に働ける環境を構築できるほか、従業員に「緊急事態時に備えて、事業縮小・倒産のリスクを回避する経営体制を構築している」と認識してもらいやすくなるため、会社への信頼度向上が期待できます。また、人材の流出を防ぐ効果も生まれるでしょう。
事業縮小や倒産のリスクを軽減できる
さまざまな対策を行っていても、緊急事態により事業活動が停止するリスクをゼロにすることは難しいでしょう。しかし停止期間が長くなりすぎると、販売先や仕入先などとの取引関係が途絶えてしまう可能性があります。最悪の場合、事業再開の目途が立ったときにはすでに競合他社と関係を築いており、自社との取引復活が見込めない状況になることもあるでしょう。
事業継続計画(BCP)を策定していれば、緊急事態に直面し事業の継続が危ぶまれたとしても、一早く立て直すことが可能です。取引関係の断絶を防ぎやすくなるため、事業縮小や倒産のリスクを軽減できるでしょう。
自社の中核事業や強み・弱みを明確にできる
事業継続計画(BCP)を策定する際は、まず自社内の事業のうち「会社の存続にかかわる最も重要性(または緊急性)の高い事業」、つまり「中核事業」を明確にする必要があります。これにより、社内でビジネスの優先順位に対する共通認識を持てるようになるため、平常時から経営資源の投入やリソース配分の判断などを適切に行えるようになります。
また、事業継続計画(BCP)策定するプロセスの中で、中核事業が持つ強みやリスクなどの弱みも把握できるようになるため、経営戦略の進展も期待できるでしょう。
取引先や顧客からの信頼を獲得できる
もし緊急事態の発生により事業活動が停止した場合に、事業継続計画(BCP)が策定されていないことが取引先や顧客に伝わってしまうと、「想定外に備えていない危機管理意識の低い会社」というイメージを持たれてしまい、評価が下がる恐れがあります。
そこで事業継続計画(BCP)を策定していれば、緊急事態時においても事業の維持および早期復旧が望めるだけでなく、リスクマネジメントに対する意識の高さのアピールにもつながります。取引先や顧客から信頼を獲得しやすくなるため、企業価値の向上も期待できるでしょう。
事業継続計画(BCP)策定の4つの手順

ここでは、事業継続計画(BCP)策定のための具体的な手順をご紹介します。
1.プロジェクトチームの編成
事業継続計画(BCP)はその性質上、自社におけるさまざまな部門が関わって作成すべきです。一般的には、各部門から人員を招集し、プロジェクトチームを編成して進めます。例えば総務部など、取りまとめをおこなう部門が事務局となり、全体の進捗管理や作業量の配分などをするケースが多いようです。
2.優先する中核事業の選定
自社のさまざまな事業のうち、「会社の存続にかかわる最も重要性(または緊急性)の高い事業」、つまり自社の中核事業を選定します。
中核事業の選定には、会社において重要と思われる事業をいくつか挙げて、その中から優先順位をつけていきます。
事業に優先順位をつける際のポイントは2つで、それは「重要度」と「頻度」です。もしその事業がストップした場合、どれだけ自社に損失を与えるのか、またその事業はどれ位の頻度で発生するものかという2つの視点で判断します。
次に、中核事業の継続に特に必要な経営資源(ヒト・カネ・モノなど)を思いつく限り洗い出しておきます。
3.中核事業が受ける被害を想定する
自然災害などの発生時、選定した中核事業がどの程度の影響を受ける恐れがあるのかを想定します。自然災害は地震や風水害などが挙げられますが、中核事業に関連する部門所在地における自然災害の発生率を調査し、災害の種類によって中核事業や経営資源がどれ位の影響を受け、事業継続にどの程度支障を及ぼすのかを想定します。
また被害を受けた際に、建物や設備の復旧にはどれ位の費用と時間が必要か、また復旧までの事業中断期間の損失はどの程度かも、あらかじめ分析しておきましょう。
4.復旧に向けた動き方を決める
被害発生からの復旧に着手する時、まず自社内で「どのように動き始めるか」を考えておきます。一般的に、初動は「現状把握」です。どこに、どのような被害が発生したのか把握し、中核事業の継続に不足するであろう“モノ”や“情報”を見極めます。また現状把握には、部署を超えた情報共有および協力体制が欠かせません。有事において、迅速に行動を開始できる体制を整え、事業継続計画(BCP)にも明記しておくことが大切です。
現状把握の完了後は、「移行・代替」の段階に移ります。どの部門が中核事業の代替対応やバックアップをおこなうか、その対応にはどのような事前準備が必要かなど、事業継続するための対応策を明らかにします。
その後は、業務を「復旧」するための動きを考えます。設備やネットワーク構築といった物理的・技術的な復旧をどの手順でおこなうのか、復旧に必要な情報は何かを洗い出しておきます。
事業継続計画(BCP)を機能させる5つのポイント

事業継続計画(BCP)を効果的に機能させる5つのポイントをご紹介します。
1. 事業継続計画(BCP)対策の対象は中核事業に絞る
事業継続計画(BCP)の策定範囲は、企業収益の大半を占め、会社の存続に影響を及ぼす中核事業に絞ります。なぜなら、中核事業の早期復旧は、収益面の安定に直結するためです。事業数の多い企業ほど、事業継続計画(BCP)における選択と集中、策定範囲の見極めが重要となります。
2.顧客と協議をして目標を定めておく
事業継続計画(BCP)を策定していても、緊急事態時に中核事業を即座に平常時と同じレベルまで復旧させることは困難です。顧客とあらかじめ「緊急事態発生からどの程度の時間で、平常時の何割程度までの事業復旧を目指すか」を協議して、目標設定をおこなっておきます。
目標の設定には、顧客との関係や社会に与える影響などを考慮して決めることをおすすめします。ただし、顧客や社会が求める「どの程度の時間で、平常時の何割程度の事業を復旧してほしい」という要望に、必ずしも応えられるわけではありません。
実際には実行が不可能だと思われるような計画では、顧客の信頼は得られません。また緊急事態時に「計画通りに進まない」と現場を一層混乱させることにもなりかねません。
復旧対策に必要なコストは許容範囲内か、計画通りに実行できる人材や環境は確保できそうか、社内だけでなく社外との協力体制がとれるのか、といったことを一つひとつ確認していきましょう。現実と目標とのギャップを認識したうえで、あらためて実際に実現可能な目標を設定することが必要です。
3.具体的な動き方を明らかにする
事業継続計画(BCP)にまとめる緊急時の動き方は、具体的に明記します。抽象的な内容では、有事の際に現場の混乱を加速させます。「〇〇発生時は××をする」といったように、予測できる局面別での動き方を、簡潔かつ具体的に明示すると良いでしょう。
中核事業を継続するためには、製造拠点やサプライヤーが被災した場合など、さまざまな事態を想定して代替案を策定しておくことも重要です。
関連記事
4. 事業継続計画(BCP)対策に沿った対応訓練を実施する
事業継続計画(BCP)は、策定しただけでは意味がありません。常日ごろから内容を周知することに加え、定期的な訓練や講習会を実施し、役職に関係なく全従業員の意識向上をはかります。また、被害を最小限におさえるための防災訓練の観点では、自治体や消防署との共同訓練なども有効です。
5.策定した事業継続計画(BCP)と運用状況を検証する
策定した事業継続計画(BCP)は定期的に見直しをおこない、改善し続ける必要があります。見直しの際に活用できるのが、中小企業庁のウェブページ「中小企業BCP策定運用指針」にある「基本コース」です。
同ページでは、BCP策定や運用状況の自己診断をおこなうことができます。計66の質問に対し、「はい」か「いいえ」で回答するチェックシート形式のページです。回答結果を参考に、策定したBCP策定・運用状況の自己診断に問題がないかの確認に有効です。
業界別に見る事業継続計画(BCP)の具体例
ここでは、製造業・販売業・金融業・建設業・運輸業、介護施設、それぞれの事業継続計画(BCP)の具体例をご紹介します。
製造業
生産計画の策定から始まり、原材料の調達、生産設備の稼働、出庫・納品指示、出荷後の情報管理など、数多くの工程で成り立っている製造業。緊急事態の発生によりどれかひとつの工程でもが停止すると、全体に影響が及ぶ可能性があります。そのため、事業継続計画(BCP)の必要性は極めて高いと言えます。
製造業の事業継続計画(BCP)には、以下のような項目が挙げられます。
- 原材料や部品をひとつに絞らず、代替品や複数の調達先を検討する
- 生産設備のバックアップ(性能や構成・データの内容などが同一のもの)を準備する
- 納品物の出荷ルートや物流拠点に関して、メインのほかにも複数検討する
販売業
販売業は日々移り変わる市場変化に対応しなければならないため、事業継続計画(BCP)が後回しになりがちです。しかし、顧客と直接コミュニケーションを取ることが多いからこそ、サービスの継続や品質維持に重きを置いた事業継続計画(BCP)が求められます。
販売業の事業継続計画(BCP)には、以下のような項目が挙げられます。
- 店舗や倉庫の耐震化および防災設備の導入・整備を推進する
- ECサイトの開設やデリバリーなど、店舗以外の販売チャネル開拓する
- 商品や資材の在庫管理および配送計画の見直し
金融業
金融業は、企業の資金管理や決済など、経済活動に深く関わるサービスを扱っています。こうしたサービスが緊急事態の発生により停止した場合、社会に大きな混乱を与えることは確実でしょう。そのため、事業継続計画(BCP)の策定は必須と言えます。
金融業の事業継続計画(BCP)には、以下のような項目が挙げられます。
- 店舗やATMの安全確保・防災対策を促進する
- オンライン(モバイル)バンキングをはじめとする非対面型サービスを構築する
- システムのバックアップ策を複数確保すると共に、クラウド化を促進する
建設業
建設業は、人々の暮らしに直結するインフラを作り整備する仕事です。特に災害時は仮設住宅の建設などを担うことから、緊急事態時でも事業を継続することが強く求められます。
建設業の事業継続計画(BCP)には、以下のような項目が挙げられます。
- 工事現場や資材置場の安全確保や、防災対策を促進する
- 協力会社などとの連携を強化し、お互いに支援できる体制を構築する
- 従業員の安全教育を強化する
運輸業
物流や交通を担う運輸業は、緊急事態時に道路が分断される可能性を考慮して事業継続計画(BCP)を策定する必要があります。また、従業員がさまざまな地域を移動しながら業務に従事する傾向があることから、従業員の現在位置の確認と安全確保にも努めることが重要です。
運輸業の事業継続計画(BCP)には、以下のような項目が挙げられます。
- 運送ルートや運行計画の見直し・改善・多様化を検討する
- 道路分断時の代替手段を検討し、他社との協力体制も検討する
- 従業員の現在位置を把握できる体制構築と共に、各自の安全教育を強化する
介護施設
介護施設は、高齢者や要介護者の生活を24時間365日支える重要な社会インフラです。入居者や利用者の多くは自力での避難が困難であり、医療的ケアを必要とする方も少なくありません。そのため、緊急事態が発生しても介護サービスを継続することが、利用者の生命に直接関わる極めて重要な課題となります。特に停電による医療機器の停止や、職員不足によるケアの質の低下は、深刻な事態を招く可能性があるため、綿密な事業継続計画(BCP)の策定が不可欠です。
介護施設の事業継続計画(BCP)には、以下のような項目が挙げられます。
- 非常用電源の確保と医療機器のバックアップ体制を整備し、十分な燃料備蓄を確保する
- 近隣施設や医療機関などとの相互支援協定を締結し、職員の応援派遣や利用者の一時受入れ体制を構築する
- 食料・医薬品・衛生用品の備蓄を最低3日分、可能であれば7日分を確保し、複数の調達ルートを確立する
関連記事
事業継続計画(BCP)対策の課題と問題点

緊急事態時に中核事業を継続、または、早期に復旧させるために有効な事業継続計画(BCP)ですが、課題や問題点もあります。
事業継続計画(BCP)対策はコストがかかる
有事の際に機能する事業継続計画(BCP)を策定するには、綿密な下調べ、さまざまな部署からの人員の協力、顧客との協議、コンサルティングなどが必要です。さらに策定後にも定期的な見直しや、実際に計画が実行できるようにするための投資や従業員の教育が必要です。
これらには人件費をはじめとするコストが発生します。いつ起こるかわからない緊急事態に対してコストをかけて対策をするのは、財政面から難しいと考える企業も少なからず存在します。
しかし、自治体や各種団体で補助金や助成金の制度が設けられているケースもあります。例えば、公益財団法人東京都中小企業振興公社が設けている「BCP実践促進助成金」などがあります。中小企業者などが策定した事業継続計画(BCP)を実行するために必要な物品・設備などの導入に要する経費の一部を支援する助成金です。このような自社で活用可能な制度がないか調べてみるものよいでしょう。
事業継続計画(BCP)が機能しない可能性も
「トラブルの実態にマッチする適切な事業継続計画(BCP)が策定できていなかった」「事業継続計画(BCP)の想定を超える事態が起きた」などという場合、事業継続計画(BCP)が機能しないことも起こり得ます。検討の段階でできるだけ多くの事態を想定し、実現可能の高い事業継続計画(BCP)を策定することが必要です。
まとめ

自然災害をはじめとした緊急事態はいつ発生するかわからず、人の手でコントロールすることもできません。早期に事業継続計画(BCP)を策定・周知し、内容を定期的に見直すことで、有事においても事業を継続・早期復旧できる体制を整えることをおすすめします。また同時に、策定したBCP計画を実行するためにも、まずは命を守るための防災備蓄品の確保も万全に行っておきましょう。
パソナ日本総務部では、主に総務部が管轄する企業のリスクマネジメントを支援するサービスを提供しています。具体的には、防災備蓄品の購入や買い替え、在庫管理システムの提供や棚卸し・在庫管理など管理面のサポートを実施しています。
自然災害の発生頻度が高い日本において、企業のリスクマネジメントは必須事項です。この機会に、ぜひ一度ご相談ください。



