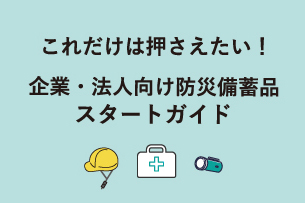【防災備蓄品リスト】企業と家庭それぞれに向けて全19アイテムを徹底解説!
【防災備蓄品リスト】企業と家庭それぞれに向けて全19アイテムを徹底解説!

地震や台風などの災害が発生した時に備えて、日ごろから防災備蓄品を準備しておく必要があります。とはいえ、準備しておくべき備蓄品の種類や数量が分からない場合も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、災害時に有用な備蓄品を紹介し、重要性や管理のコツなどについて詳しく解説していきます。
防災備蓄品の重要性とは?

災害時の備蓄の有無は、いざという状況での生活の質を大きく左右します。多くの自治体では有事に備え避難所に防災備蓄品が用意されているものの、十分な量の物資が全員に行き渡るほど潤沢には確保されていない場合がほとんどだと言われています。
また災害の程度によっては、自宅や会社などの場所から移動することが物理的に困難となり、助けが来るまでその場にとどまらざるを得ない場合もあります。
東日本大震災など過去の災害においても、各被災地へ支援が行き渡るのに多くの時間がかかり、スーパーなどでは水や食料の売り切れなどの物質不足が問題になりました。
大規模なライフラインの停止など、災害時には何が起こるか分かりません。水や食料はもちろん、日用品や衛生用品なども日ごろから備蓄しておくことが、災害時に身を守る最も有効な手段であるとされています。
なお、オフィスにおける災害対策については他にもコラム内でご紹介しています。有事対応を担う企業担当者の方々は、ぜひ以下のリンクも確認してください。
関連記事
【必須】防災備蓄品リストと必要な量の目安

続いては災害時に必要な防災備蓄品をリスト形式でご紹介します。
農林水産省発表の「災害時に備えた食品ストックガイド」によると、最低3日分から1週間分を想定した備蓄品が必要であるとされています。一般的に災害発生~ライフライン復旧までにかかる期間は1週間程度とされており、災害時支援物資の到着にも3日以上はかかる可能性が大きいためです。
ここでは上記の基準に照らし合わせ、「大人1人あたりに必要な3日間分の備蓄品の量」をご紹介します。
防災備蓄品リスト(3日分)
- 水…9リットル
- 食料品…9食(主食、副菜、栄養補助食品含む)
- 簡易トイレ…15セット(1日5回使用の場合)
- トイレットペーパー…3ロール
- 常備薬…各1箱(解熱鎮痛剤、総合感冒薬、軟膏、包帯、湿布など)
- 毛布…1枚
- ラジオ…1台
- モバイルバッテリー…1台
- 懐中電灯…1台
- 電池…1箱(10本入)
それぞれについて詳細に解説いたします。
水…9リットル
水分は生きる上で欠かせない最重要の資源です。災害発生時には断水などが生じることも想定されるため、大人1人あたりに必要とされる「1日3リットル」の飲料水を最低でも確保しておくことが大切です。
食料品…9食(主食、副菜、栄養補助食品含む)
水分と同じく、生命維持に欠かせないのが食料品です。保存性に優れた非常食や調理の手間がかからない栄養補助食品などを少なくとも9食分ストックしておくことをおすすめします。
具体的な食品や管理方法については以下のコラムでも詳しく解説しています。
簡易トイレ…15セット(1日5回使用の場合)
災害発生時に直面する問題のひとつが「排泄」に関わるものです。被災時にトイレを普段通り利用することは難しいと想定されるため、日に最低5回の利用を想定し1人あたり5セット×3日分を準備しておくと良いでしょう。
トイレットペーパー…3ロール
簡易トイレとセットで必要となるのがトイレットペーパーです。排泄時はもちろん、緊急時のティッシュペーパー代わりにもなるため、1日に1ロール消費する前提で備えておくと良いでしょう。
常備薬…各1箱(解熱鎮痛剤、総合感冒薬、軟膏、包帯、湿布など)
被災時には環境の変化による体調不良や外傷など、さまざまなリスクが懸念されます。救助までの応急処置としても、鎮痛剤や包帯、湿布、常備薬などを1箱ずつ準備しておくと安心です。
毛布…1枚
災害発生から救助までの間、少なくとも数日は過酷な環境下で過ごさざるを得ない可能性があります。睡眠時や保温のために、毛布を1人1枚ずつ準備しておくことをおすすめします。また、毛布は寒さが厳しい時だけでなく、床面が荒れている際などさまざまなシチュエーションで役立ちます。
ラジオ…1台
スマートフォンやパソコンの使用が現実的でない被災時において、貴重な情報源となるのがラジオ放送です。被害状況や救助時間の目安を把握するために、1台備えておくと良いでしょう。
モバイルバッテリー…1台
上記でスマートフォンやパソコンの使用が現実的でないと述べましたが、インターネット回線のエラーだけでなく電力不足も予想されます。各自モバイルバッテリーを1台は準備しておき、もしもの時に備えましょう。
懐中電灯…1台
備蓄品の中でも特に重要なのが懐中電灯です。停電が大きな問題となる災害発生時には、唯一の光源となります。持ち運びが簡単で、場所移動の時にも土砂崩れや家屋の崩落などによる道の荒れを確認し、事故やけがのリスクを軽減することに役立ちます。
電池…1箱(10本入)
単3電池・単4電池など汎用性の高い電池も、備えておきたいアイテムです。電池交換式のモバイルバッテリーや懐中電灯、ラジオなどさまざまな機器の駆動に欠かせません。
以上が、災害時に最低限必要な3日分の備蓄品です。食料品と衛生用品、情報源の確保は特に重要とされています。このほかライフラインの断絶に備えるため、カセットコンロや生活用水を補給する給水袋などを備えておくことも有効です。
非常食にはなるべく調理を必要としないカンパンや缶詰、アルファ米などを選び、栄養補助食品も備えておくと良いとされています。
【推奨】企業が準備しておきたい備蓄品リスト

「もしもの時」はいつ来るか想像できず、会社での勤務中に起こるかもしれません。従業員が会社にいる時に被災し、交通機関の停止によって帰宅できない事態に陥ることも考えられます。
十分な災害対策は、従業員の身の安全確保はもとより、被災後の事業継続を左右すると言えるでしょう。また地域社会の一員として、地域住民の支援を行うことも企業の社会責任だと言えます。
ここでは、オフィスや事業所で特に備えておくべき備蓄品をご紹介します。
オフィスの備蓄品リスト
- 救助道具
- ヘルメット・手袋・グローブ
- 応急手当セット
- レインウェア
それぞれについて詳細に解説いたします。
「救助道具」で従業員の安全を確保
事業所の倒壊や設備の損壊から従業員を守るためには、「救助道具」を準備しておくことが大切です。
厚みのあるガラスを破るハンマーや重量物を持ち上げられるような工具を準備しておけば、建物やオフィス家具、設備などの下敷きとなった人や閉じ込められた人の救出ができるようになります。さらに、近隣で働く人や住民の救援にも役立てられるでしょう。
救助道具の代表的なものは以下の通りです。
- バール
- のこぎり
- ジャッキ
- つるはし
- スコップ
- ハンマー
- 救出ロープ 他
救助道具セットは、法人事業者向けとして販売されているものもあります。オフィスや事業所ごとで購入し、すぐに取り出しやすいところに保管しておくことが重要です。加えて、従業員が万一の際に困らないよう、使い方の研修を事前に実施しておくことをおすすめします。
「ヘルメット」や「手袋・グローブ」で身の安全を守る
従業員の身の安全を確保するためには、「ヘルメット」「手袋・グローブ」の準備も有効だと考えられます。防災用としてヘルメット、手袋やグローブを選ぶ際には、安全基準や保管のしやすさなどがポイントです。
防災用ヘルメットの場合は、厚生労働省の「保護帽の規格」という項目をチェックしておくと良いでしょう。規格としては、落下するがれきから頭部を守る「飛来・落下物用」と、転倒や落下時の衝撃から頭部を守る「墜落時保護用」という2つの項目があります。両方の規格に合格していることが望ましいですが、少なくとも飛来・落下物用の試験に合格しているものを選ぶことが重要です。ヘルメットの保管にはスペースが必要になりますが、折りたたみタイプのヘルメットであれば、省スペースでコンパクトに備えられます。
手袋やグローブは、がれきが散乱する中で避難、救助する際に欠かせないものです。布製の軍手ではなく、刃物を触っても切れないほど丈夫な「防刃手袋」を選ぶと良いでしょう。手袋が切れにくいかどうかを判断するには、製品の「耐切創レベル」を確認し、レベルが最大値の手袋を選ぶと安心です。
「応急手当セット」でけがなどのトラブルに対応
「応急手当セット」も重要度の高い災害備蓄品で、使用人数に合わせて十分な数を準備することが大切です。応急手当セットの基本的なアイテムには、下記のようなものがあります。
- 絆創膏
- 消毒液
- ピンセット
- 包帯
- ガーゼ
- 三角巾
- サージカルテープ
- 体温計
- マスク 他
応急手当セットの選び方のポイントとしては、けがをした人のところにすぐに駆けつけられるという「運びやすさ」があります。ポケットサイズのもの、カバンやリュックにまとめられたものが持ち運びに便利です。
企業が遵守しなければならない「労働安全衛生規則」では、「事業場において発生することが想定される労働災害等に応じ、応急手当に必要なものを備え付けること」との記述があります。職場の環境は事業者ごとに異なるため、それぞれの環境に適したものを備え付ける必要があります。
「レインウェア」で天候災害や防災対策を

近年は、ゲリラ豪雨や巨大台風といった異常気象による水害も増加しています。従業員の人数分以上の「レインウェア」を備えておけば、水害時に移動せざるを得ない場合の安全性が高まるでしょう。
傘と比べ、レインウェアのメリットは身体が濡れにくいことです。水に濡れると身体が冷えて体力が奪われるため、水害時にはレインウェアの方が適していると考えられています。両手が空く形になるため雨の中の避難や救助作業の際にも便利で、冬季の保温対策としても役立ちます。
防災のためのレインウェア選びでは、防水性と透湿性、動きやすさなどがポイントになります。水をはじき、ムレにくいものであれば長時間快適に過ごせます。目安として「耐水性10,000m以上」「透湿性8,000g以上」と示されているものが、災害時に使用するレインウェアとしておすすめです。
加えて上着とズボンが別々になったセパレートタイプであれば、動きやすいだけでなく転倒防止にもなります。
【推奨】家庭に用意しておきたい防災備蓄品リスト

「もしもの時」は、近い将来、もしかすると今すぐ起こるかもしれません。だからこそ、日ごろから用意しておきたい備蓄品は数多く存在します。ここでは、家庭に備えておくと安心で役立つアイテムをご紹介しますので、参考にしてみてください。
役立つアイテムリスト
- カセットコンロ
- ウェットティッシュ
- ラップ
- 新聞紙
- ポリタンクやペットボトル
それぞれについて詳細に解説いたします。
「カセットコンロ」で簡単な調理を可能に
ガス・水道・電気などのライフライン復旧には、災害発生から相当な時間がかかることが予想されます。そこで備えておきたいのがカセットコンロとガスボンベです。これらさえあれば、簡単な調理を行うことができます。温かい飲み物や食事は災害時の不安を和らげてくるため、被災してすぐのタイミングにも、避難生活中にも役立つ優れものです。
農林水産省のすすめでは、ガスボンベの備蓄量は大人1人あたり1週間で6本程度とされています。家族の人数分を計算して準備しておきましょう。
「ウェットティッシュ」で手指や身体を清潔に保つ
災害発生時に大きなストレスの原因となり、体調を損ねる一因となり得るのが「清潔」の問題です。身体や手指の汚れを落とせないことは、想像以上に心身への負担となります。ウェットティッシュやウェットタオルなどを常備しておけば、有事の時にも安心でしょう。
インフルエンザなどさまざまな感染症や、食中毒などへの対策という側面からも、準備しておくことをおすすめします。
「ラップ」で皿などを汚さず再利用
何気ない生活用品の一つであるラップも、さまざまな活用法がある汎用性に優れたアイテムです。お皿にラップを敷いて使用することで洗うための水を節約できる上に、段ボールや新聞紙などをラップで覆って皿にすることや、丸めてスポンジ代わりにもできます。衛生用品としても備えておきたいアイテムと言えるでしょう。
ほかにもラップを巻きつけることで、物の固定や、けがをした時の傷口の保護などに活用できます。骨折した時には添木を固定して応急処置に使うなど、さまざまな場面で活躍するでしょう。また、身体に新聞紙を巻いてその上からさらにラップを何重にも巻きつけると、防寒対策にもなります。
アイデア次第で多様な使い方ができるラップは、食品用として備蓄するだけでなく、便利アイテムとして普段から多めにストックしておくことをおすすめします。
「新聞紙」は防寒からゴミ処理まで大活躍
普段は処分しがちな新聞紙ですが、災害時には防寒対策からゴミの処理まで幅広く活躍する便利なアイテムです。トイレットペーパーや紙皿の代用品として、また燃料としてなどさまざまなシーンで役立ちます。
折り紙のように自在に変形させることができる新聞紙は、災害時用のスリッパとして活用できます。読み終わってすぐ捨てるのではなく、災害時の頼もしいアイテムとして備えておくと良いでしょう。
「ポリタンク」や「ペットボトル」で給水車からの補給をスムーズに
災害発生時から避難生活中まで、被災後のあらゆるタイミングで直面するのが「水」に関する問題です。人間が生活する上では、飲料水はもちろん生活用水としても相当量が必要となり、ライフライン復旧まで備蓄だけで乗り切るのは現実的ではないでしょう。
そこで多くの場合、被災地では給水車が出動します。給水のタイミングでスムーズに水を確保することができるよう、ポリタンクや空のペットボトル、水筒などを準備しておくことをおすすめします。
また、給水を受ける際の容器のサイズには注意が必要です。地震時には、道路が荒れている場合や、エレベーターが停止していることもあるため、重い容器を持ち運ぶためのキャリーケースが使用できるとは限りません。満水にした時に自力で持ち運べる重さであるかを確認し、持ち運び方法も検討しておきましょう。
さらに災害発生後は、どこで給水できるかを確認するのが難しいこともあるため、事前に把握しておくことも大切です。各自治体から公表されている防災マップなどで、自宅や会社の最寄りの給水ポイントをチェックしておきましょう。
防災備蓄品を管理するコツ

防災備蓄品として必要な品目と分量についてお伝えしましたが、これらは単に準備さえすれば良いわけではありません。適切に管理しておかなければ、いざという災害時に利用できない可能性もあります。特に食料品や水には賞味期限が設定されており、災害備蓄用であってもほとんどが3年から10年で賞味期限を迎えます。
いざという時に食べることができないという状況を防ぐためにも、定期的な備蓄品の管理は欠かせません。従業員や家族の人数にあわせた定期的な防災備蓄品の量の見直しや、賞味期限を適切に管理できる体制の構築を平常時から行っておきましょう。
ここでは、防災備蓄品の在庫管理や収納に関するコツをご紹介します。
在庫管理のコツ
防災備蓄品の在庫リストを作成し、定期的に更新しましょう。リストには各アイテムの数量や購入日、賞味期限や使用期限などを記載し、適切に管理します。
防災備蓄品の在庫管理にはExcelなどでリスト作成することが多いようですが、近年は手軽に導入できるクラウドシステムも普及しています。システムによっては数量が減った場合や、賞味期限が近づいた時にアラートで自動通知を行うなどの機能もあり、管理をよりスムーズに行えるようになります。
防災備蓄品の効果的な収納方法
飲料水や非常食などの重くてかさばるアイテムは、床に近い位置に置くと取り出しやすくなります。また、必要な時にすぐに見つけ出すために、食品や救急用品などをカテゴリごとに分けて整理しましょう。
小物類や軽いアイテムは、棚や引き出しの上部を利用するとスムーズに管理できるでしょう。透明のプラスチック製コンテナを使い、ラベルを貼って分類しておくと、一目で中身が分かるため便利です。定期的にチェックして、古くなったアイテムを更新することも忘れずに行いましょう。
企業防災の観点では、災害発生時にエレベーターの停止などにより運び出しが困難になる場合があるため、広いオフィス内のうち一箇所に備蓄品の保管を集中させることは望ましくありません。なるべく各フロアに備蓄品を分散して設置し、速やかに全員に物資が届くような体制を整えることが大切です。
そして、防災備蓄品の設置場所は従業員全員へ共有し、防災訓練を通じて実際に取り出す練習をすることをおすすめします。これにより、災害時に素早く対応できるようになります。
防災備蓄品の定期的な点検とメンテナンスも忘れてはいけません。特に非常食や飲料水、防寒具など消耗品の期限管理には注意が必要です。在庫管理ツールやローリングストック法などを活用し、効率的な備蓄品管理を実現しましょう。
「ローリングストック法」とは
ローリングストック法とは、平常時から非常食などの備蓄品を期限切れ前に都度消費し、使った分を継続的に補充するという方法です。
ローリングストック法のメリットは、備蓄品をいつでも使える状態に保ちつつ、常に一定量の備蓄品を備えておく体制を整えられることです。
デメリットとして、企業がローリングストック法を運用するには、従業員の人数にもよりますが多くの備蓄品と購入コスト、保管するスペースが必要になることが挙げられます。
防災備蓄品の保管方法については以下のコラムでも詳しく解説しています。
外部委託を活用した管理方法もおすすめ
防災備蓄品の管理は日ごろの整理整頓や定期的な見直し、メンテナンスが必要です。しかし、これを日常業務と並行して行うには時間と手間がかかるため、多くの企業で専門会社に外部委託(アウトソーシング)するケースが増えています。
外部委託を利用するメリットとして、専門知識に基づいた効率的な在庫管理や、最新トレンドに基づいた備蓄品の提案を受けられる点があります。また、定期的なチェックと更新作業を委託することで、期限切れの備蓄品の発生リスクを減らすことが可能です。
企業の防災備蓄品活用事例
ここではパソナ日本総務部の「防災備蓄品ワンストップサービス」を導入した2社の事例を紹介します。
大手外資系コンサルティング会社
東京本社および全国拠点において約8,000名を対象に防災備蓄品の一斉入れ替えを実施することになったものの、各拠点の整備状況が把握できていませんでした。さらに不要になった備蓄品の廃棄コストを削減したいという課題を抱えていたそうです。
そこでパソナ日本総務部が備蓄倉庫の棚卸しを行い、備蓄品の一覧リストを作成することで現状を可視化。その上で期限切れが近い備蓄品を優先的に選別し、新たな備蓄品を選定・提案するとともに、備蓄倉庫への搬入計画を策定し、納品の立ち会いまで対応しました。さらに、期限切れ間近の備蓄品については無料で引き取りを実施することで、廃棄コストの削減にも貢献しました。
大手ホテルチェーン
こちらの大手ホテルチェーンはホテルの新規開業対応に追われ、防災備蓄品の整備まで手が回らない状況でした。また、既存施設の備蓄品の整備状況にもバラつきがあり、一律の基準で管理する仕組みが必要とされていたようです。
そこでパソナ日本総務部は、全国のホテルで統一した備蓄品ラインナップを考案・提案することで、整備の抜け漏れを防ぐとともに、新規開業時にもスムーズに防災備蓄品を備えられるようサポートしました。さらに、シンプルな操作で利用できる防災備蓄品管理システム「kuranosuke(くらのすけ)」で各拠点の整備状況を一元管理することで、リアルタイムでの見える化を実現しました。加えて、有事の初期対応マニュアルの策定支援も行い、BCP対策の強化にも貢献しました。
まとめ

災害はいつ発生するか予測が難しい点に、その恐ろしさがあります。企業活動の上でも、事業継続の阻害や従業員の生命が侵害される可能性があり、防災備蓄品の整備をはじめとするBCP対策は重要な経営課題のひとつであると言われています。
パソナ日本総務部では、「防災備蓄品ワンストップサービス」として企業向けの防災ソリューションを提供しています。法人向け防災備蓄品の管理や補充、期限切れ間近の備蓄品引取りなどをトータルサポートし、企業の災害対策をバックアップする防災分野のアウトソーシングサービスです。
「災害対策の重要性は認識しているが、対応が後手に回ってしまっている」という企業担当者の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。