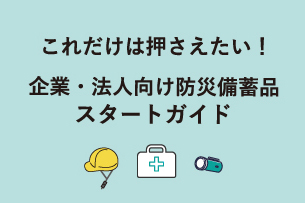賞味期限切れ間近の防災備蓄品はどうする?寄付など廃棄処分を防ぐ方法や予防策を紹介
賞味期限切れ間近の防災備蓄品はどうする?寄付など廃棄処分を防ぐ方法や予防策を紹介

防災備蓄品として整備される食料品の賞味期限はとても長いですが、幸いにも災害が発生せず、使用しないまま賞味期限を迎えた場合は廃棄することが一般的です。しかし、単純に期限切れ防災備蓄品を破棄してしまうと、世界的な課題であるフードロスにつながりかねません。このことから、防災備蓄品の処分方法に頭を悩ませる企業の防災担当者も多いのではないでしょうか。 防災備蓄品の破棄を防ぐ方法には、社員への配布やフードバンクへの寄付など、いくつかの方法があります。 この記事では、期限間近の防災備蓄品をどのように扱えばよいのか、単純な破棄を防ぐ方法や、フードロスを削減するための今後の改善対策までまとめて解説します。
賞味期限切れの防災備蓄品はどうする?
賞味期限が切れてしまった防災備蓄品はどうすればよいのでしょうか?
企業で管理している防災用品の賞味期限が切れた場合、まずフードバンクなどへの寄付は一般的に受け付けられないことに留意する必要があります。賞味期限内の段階で寄付や他の活用方法を検討すれば、廃棄コストの削減や社会貢献につながります。
一方、賞味期限を過ぎた食品を大量に廃棄する場合は、一般ごみとして廃棄できない場合もあり、産業廃棄物として専門業者に依頼する必要があります。この際には廃棄費用が発生するため、担当者は廃棄コストを見積もったうえで予算管理を行いましょう。また、廃棄前には内容物が腐敗や液漏れを起こしていないか確認し、衛生基準を守りながら適切に廃棄することが重要です。期限管理を徹底し、早めに入れ替えや他の活用策を検討することで、無駄なコストや作業負担を軽減できます。
防災備蓄品の賞味期限の目安
防災備蓄品の賞味期限は、種類や保存状態によって異なります。一般的には3~5年程度のものが多いですが、商品によってはそれ以上長期保存できるものもあります。ここでは代表的な防災用食品を例に、賞味期限の目安と管理上の押さえておきたいポイントを解説します。
缶詰類
缶詰は、一般的に賞味期限が3年程度ですが、加工方法や内容物によっては5年程度保存可能なものもあります。保管する際には、直射日光や高温多湿を避け、定期的に缶の変形や錆を確認しましょう。特に凹みや傷があると品質が損なわれる可能性があるため、早めの使用や入れ替えが望ましいです。
レトルト食品
レトルトカレーやおかゆなど、加圧加熱処理が施されたレトルト食品は、一般的に3~5年程度の賞味期限が設定されています。パッケージの破損がなければ比較的安定しています。
アルファ米
アルファ米は非常食の代表格で、5年程度の長期保存が可能です。開封後は湿気などにより劣化が進むため、使用する際には注意が必要です。調理が簡単でアレンジがしやすい一方、賞味期限を過ぎると風味や食感が損なわれる可能性があるため、期限表示を定期的に確認しましょう。
保存水
保存水はメーカーによって3~5年、あるいはそれ以上の賞味期限が設定されている商品もあります。ペットボトルタイプの場合、容器の素材によって経年劣化が進む可能性があるため、直射日光を避けて保管し、定期的に交換することが重要です。非常時の飲料としてだけでなく、手洗いや清掃など様々な用途に活用できます。
ビスケット・クラッカー類
ビスケットやクラッカーは空腹をしのぎやすい炭水化物源として、3~5年程度の長期保存が可能な商品が増えています。湿気を嫌うため、密閉容器に入れて直射日光や高温多湿を避けることが大切です。
非常用パン
缶やアルミパウチに入った「非常用パン」は、多くの商品が3~5年程度の賞味期限を持ち、災害時に手軽に食べられる利点があります。特殊な包装技術により空気や湿気を遮断し、品質を保っています。開封後はすぐに消費する必要があるので注意しましょう。
防災備蓄品も関係する世界的なフードロス問題

賞味期限の切れた防災備蓄品の廃棄によって生じる問題のひとつに、フードロス問題があります。
世界では毎年13億トンもの食品が消費されずに捨てられており、廃棄処理のためのコストや、処理時に発生する二酸化炭素の排出による環境破壊が社会問題となっています。
このように、生産した食品を廃棄する現状がある一方で、満足な食事が取れず、飢餓に苦しむ国が存在しているという矛盾も抱えています。
日本においてもフードロス問題は深刻で、1年間の食品廃棄量は612万トンにものぼっています。この612万トンを国民1人あたりに換算すると、毎日お茶碗1杯分の食品を廃棄している計算になります。
政府、企業、個人が一体となってフードロス問題への意識を高め、解決に導くための行動を取ることが求められる中で、不測の事態に備えて整備する防災備蓄食料の破棄について、課題感を持つ企業も増加しています。
防災備蓄品の廃棄処分を防止する3つの方法
企業が不測の災害などに備えて整備する、防災備蓄品にも賞味期限があります。賞味期限が近くなると古いものを廃棄し、新しいものと入れ替えることが一般的です。しかし、企業で整備する防災備蓄品の量は規模に比例して多くなりがちで、前述のフードロス問題から単純に産業廃棄物として廃棄することに課題を持つ企業も多くあります。
ここでは、できるだけ備蓄品の廃棄を防ぐための3つの方法について解説します。
社員に配布する
防災備蓄品の廃棄を防ぐ方法のひとつに、社員に配布するという方法があります。
一般的に、防災備蓄品は賞味期限を完全に過ぎてから入れ替えるのではなく、ある程度は賞味期限が残っている時点で入れ替えることが多いようです。まだ十分に食べられる状態の備蓄食品を社員に配布すれば、企業と社員の双方にとってメリットがあります。
最近の防災備蓄食料には数多くの種類があり、開封してそのまま食べられるものや、水やお湯で戻して食べるものなどさまざまです。これら備蓄食品をあえて平常時に食べてみることで、使用方法を学んだり味に慣れたりすることができ、不測の事態発生時への心構えができます。
また、実際に食べてみた感想をアンケート集計すれば、入替えのため新たに購入する備蓄食品を選ぶ際の有益な参考情報にもなります。会社からの福利厚生の一環として社員へ提供することで、社員満足度の向上にもつながるでしょう。
フードバンクへ寄付する
賞味期限内の防災備蓄品は、フードバンクへ寄付するという選択肢も考えられます。フードバンクには食品の品質自体には問題がないものの、さまざまな事情で販売や消費が難しい食品が集められ、必要な人のもとへ届けられる活動として注目を集めています。
フードバンクは元々海外で広まっていた考え方ですが、近年では国内にも多くの組織や関連団体が登場しています。単に廃棄するのではなく、フードバンクへ寄付して必要な組織や家庭に渡る道筋を立てることで、フードロスを削減しつつ食糧難や貧困に苦しむ人たちの助けとなるでしょう。
消費者庁でも、国内のフードバンク活動団体が一覧で紹介されています。
フードバンク活動等
なお、フードバンクに寄付できる食料品は、それぞれの受け入れ団体によって異なります。フードバンクに防災備蓄食料の寄付を検討する際は、まず最寄りのフードバンクの受け入れ条件などを確認するようにしましょう。
引き取りサービスを実施する業者に依頼する
社員への配布やフードバンクへの提供が難しい場合には、賞味期限切れ前の備蓄品を引き取ってくれる業者に依頼する方法もあります。
近年では、防災備蓄品の手配から回収までの一連の工程をアウトソーシング事業として請け負う事業者が登場しています。備蓄品の回収については事業者によって対応できる備蓄品の種類や、有償・無償の区別が異なるため、事前に調べておくことをおすすめします。
パソナ日本総務部では、防災備蓄品ワンストップサービスを提供しています。パソナ日本総務部では防災備蓄品の新規購入を条件に、期限切れ前の備蓄食料を原則無償で引き取るサービスを実施しています。これから防災備蓄品の入れ替えを検討している方は、一度問い合わせてみてはいかがでしょうか。
防災備蓄品の賞味期限切れを未然に防ぐ方法とは

ここまで、賞味期限切れ間近の防災備蓄品の廃棄を防ぐ方法をご紹介しました。しかし、整備する数も種類も多くなりがちな備蓄食料の期限を、うっかり切らしてしまい廃棄せざるを得なくなったということもあるでしょう。
そこで、ここからは防災備蓄食料の期限切れを事前に防止する対策について解説します。
ローリングストック法による管理
ローリングストック法とは、日ごろから食品やレトルト品などを少し多めにストックしておき、日常生活のなかで消費しながら、使った分を随時買い足していく方法です。古いものから順番に消費するという、主に家庭で用いられる管理方法ですが、企業での防災備蓄品の管理にもこの考え方を活用できます。
一般家庭と比べ備蓄食料の数・量ともに多い企業においては、保管スペースの整理整頓が欠かせません。例えば、新しい備蓄品を購入した時に「先入れ先出し」を意識し、古いものを倉庫内の手前に配置するよう徹底すれば、自然と賞味期限が古いものから順番に消費できる環境を作れるようになります。また、備蓄食品を保管する段ボールに、商品名だけでなく賞味期限も明記しておくと更に管理がしやすくなるでしょう。
また、エクセルなどを活用して在庫管理表を作成し、備蓄品の種類や数量、購入日や賞味期限、保管場所などの情報を一覧にまとめて定期的にチェックする体制を作ることも重要です。
防災備蓄品の管理システムを導入する
防災備蓄品の種類や量、賞味期限などを管理する専用システムを導入することも一つです。前述のエクセルによる在庫管理では、いつ・誰が・どの項目を更新したかの把握が難しく、またデータやファイルが消失するリスクもあります。
防災備蓄品の管理システムであれば、入力状況の把握が可能になりデータ消失などのリスクを抑えることもできます。さらに複数の事業所における備蓄品の管理状況を一括して見える化することもでき、業務効率の向上にもつながります。
また、システムによっては、賞味期限が切れる前にアラートメールが自動通知されるなどの機能もあるため、管理システムの導入で期限切れによる大量廃棄を未然に防止しやすくなります。
まとめ
世界的にフードロス問題が深刻化する現代において、企業においても「食品ロスを発生させない防災備蓄食料の管理」への取組みが必要不可欠です。賞味期限切れによる防災備蓄品の廃棄を未然に防止し、できるだけ有効活用するには、防災備蓄品の購入から管理、入れ替えに伴う引き取りまでを一括で対応する専門会社に対応を依頼するのがおすすめです。
パソナ日本総務部では、防災備蓄品ワンストップサービスを提供しています。防災備蓄品にかかわるフードロス削減にお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。